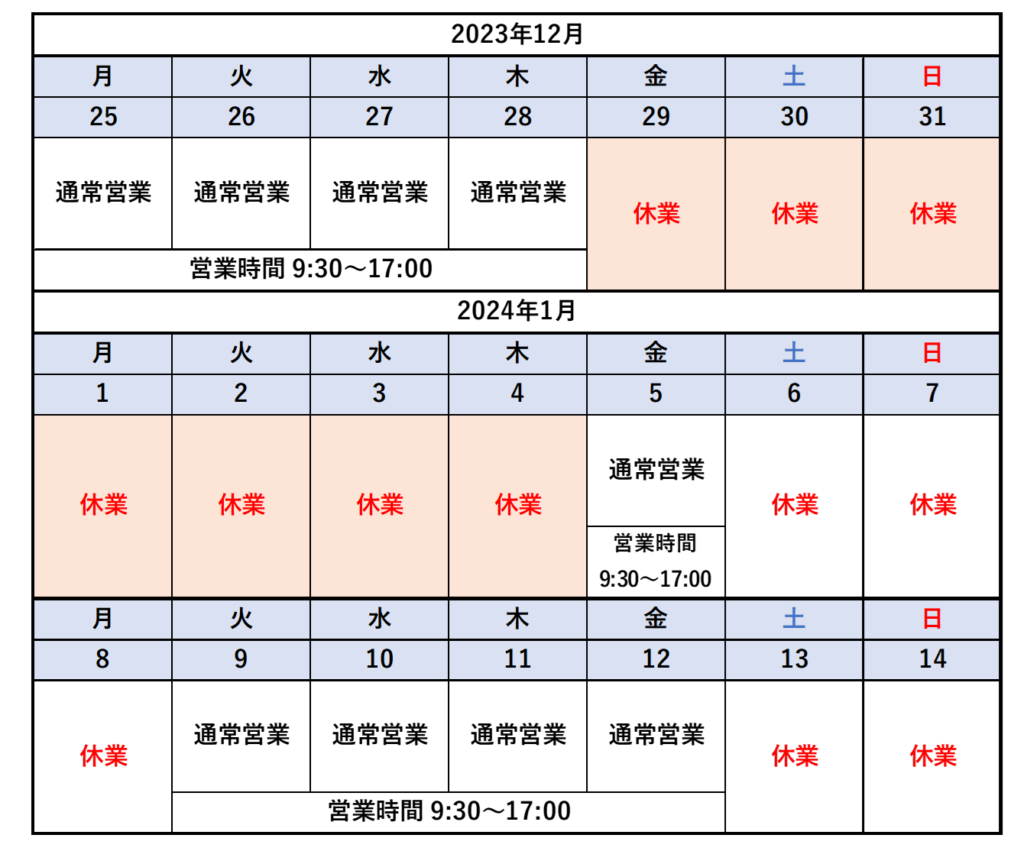植物は肥料を使用することで生長が早まったり、果実が多く美味しく実るなど、農業において作物の品質を左右する重要な成分です。
一般的に、肥料は最初から土に混ぜ込む元肥と、後からまく追肥に大別されます。また、植物によって特に必要な成分などは変わりますが、植物を育てる時に必要な成分が3種類(3要素)あります。これらは必ず肥料には含まれている大切な成分です。
本記事では、まず元肥・追肥の二種類の違いと、植物に必要な3成分について解説します。その上で、家庭菜園において行う施肥(肥料を与えること)と、水田などの露地栽培で行う元肥・追肥について例を解説していきます。
元肥・追肥とは?
元肥
元肥とは、植物の苗や苗木を植え付ける時などに、事前に土へ与えておく肥料のことをいいます。「基肥(きひ)」や「原肥(げんぴ)」と呼ばれることもあります。土に混ぜて耕す使用方法が一般的です。
植物の発育を止めずに元気に育つために施すので、すぐに効果を期待するための肥料ではありません。効果がすぐに現れない遅効性肥料や緩効性肥料を使用します。有機質肥料をよく使用するのも特徴です。
追肥
追肥とは、植物の生育状況を見ながら、不足した養分を補うために追加で与えていく肥料のことを指します。「ついひ」とも「おいごえ」とも読みます。
効果をすぐに期待するため、速効性のある液体肥料や化成肥料を使用することが一般的ですです。追肥の種類には、春先良い芽を出させることを目的にした「芽出し肥」、花を咲かせたり、実を収穫した後、弱った植物の体力を回復させるために与える「お礼肥」などがあります。
ポイント肥料切れの症状を見逃さないように気をつけて施用します。葉の色が悪くなったり、稲の場合新しく伸びた葉の色が黄色っぽくなったら、肥料切れを疑います。その他の植物だと葉や蕾が小さくなったら肥料切れのサインのため追肥を行います。
また、樹木など長い時間生育する植物には、遅効性で持続性のある肥料を使用することもあります。目的に応じた速効性肥料と緩効性肥料を使い分けが必要です。
肥料の基本三要素
植物の生育に必要養分のうち、窒素(N)、リン酸(P)、カリウム(K)は作物の生育にとって必要な量が多く、肥料として与えた際の効果が大きい特徴があります。そのためこれらは「肥料の三要素」と呼ばれます。
窒素(N):植物の葉を育てる効果
主に葉に影響する成分で、作物の生育と収穫量に最も大きく関わります。茎葉を伸長させ、葉色を濃くするため「葉肥」と呼ばれることもあります。観葉植物・葉物野菜特といった葉が中心の植物には特に窒素を与える必要があります。
窒素を過剰に与えると、逆効果で軟弱な育ちになり病害虫に負けやすくなります。また葉や茎だけ成長し果実や野菜部分への栄養が減り、収穫量が減ったり病気になりやすくなってしまうので肥料の与えすぎには注意が必要です。
リン酸(P):花や実を育てる効果
リン酸は花や実つきに関係し、「花肥」や「実肥」と呼ばれることがあります。花や果樹などには特に必要な成分で、不足すると葉枯れや果実が熟れないといった生育不良や、果実が糖度不足で甘くないといった問題を引き起こします。日本の土壌はリン酸欠乏状態のものが多いので、積極的に施用されています。
リン酸を過剰に与えると逆に草丈が伸びなくなったり、生育不良が不足したり、『微量要素』と言われるその他の生育に必要な要素である鉄や亜鉛などの欠乏症に繋がります。
カリウム(K):根の生育に関わる効果
主に根の発育を促進する成分で、「根肥」とも呼ばれます。その他にも茎を育てるだけでなく、暑さ、寒さ、病気対する抵抗性を高めます。カリウムが不足すると根の伸びがなくなり腐ってしまうことが多くなります。
カリウムが過剰になるとマグネシウム、カルシウムの吸収を阻害します。カリウムは土壌にあればあるだけ作物が吸収してしまう性質がありますが、作物の要求量は窒素ほど多くありません。そのため過剰になりやすく、与える量には特に気をつけましょう。
肥料の種類と効果
肥料にはそれぞれ効果が現れるまでの速さや原料が違っています。まず、肥料は大きく分けて有機肥料と化成肥料に大別されます。さらに、ゆっくりと長く効き目のある肥料と速効性で吸収される肥料にそこから分類されます。
化学肥料(化成肥料)
化学肥料は、科学的に窒素などを集めて肥料を作る方法で、空気中の窒素など無機物からできているのが特徴です。また鉱物や岩塩など、動物性以外のものを原料としています。最初から作物に必要な無機物の状態になっているので、水に溶けるとすぐに作物の根から吸収されます。そのため即効性が高いが持続時間が短いのが特徴です。
化学肥料の種類としては、まず前述した窒素、リン酸、カリウムがあります。割合を調整して混合させた化学肥料もあります。化学肥料は便利ですが、使いすぎると土に対して悪い影響もあります。有機肥料も織り交ぜて上手に使いこなしましょう。
有機肥料
有機質肥料は、動物や植物の堆肥などといった有機物を原料としています。動物の糞や、米ぬか、魚骨などをを微生物が分解することで肥料になります。
有機肥料には様々な種類があります。大豆などの油を原料とする油粕類、魚かすを原料とする魚粉類、動物の骨を原料とする骨粉質類などがあります。また有機肥料の中でも鳥の糞などを原料とする発酵鶏糞、草や木を原料とする草木灰は即効性が高いと言われます。
有機肥料の主な役割は、土への栄養補充・土壌改良と言われています。有機肥料は、土の中の微生物によって分解されることで、植物が吸収できる養分に変わります。そのため即効性はありませんが、効果が持続します。有機肥料は土の中の微生物の餌となることで、微生物を繁殖させます。農作物が育ちやすい土が出来るという特徴があります。
効果の出方と使用方法
肥料には、ゆっくりと長く効き目のある肥料と速効性で吸収される肥料があります。一般的には有機質肥料はゆっくりと長く効果を発揮するものが多く、化学肥料は即効性の高いものが多いと言えます。
「元肥」には有機質肥料をよく使用します。元肥には効果がすぐに現れない遅効性肥料や緩効性肥料が適しているためです。油かす、米ぬか、草木灰、腐葉土、魚粉、骨粉、堆肥といった肥料を植え付けの際に土に混ぜ込むのが特徴です。
一方で、「追肥」には化学肥料を使用することが多いと言えます。植物に不足した養分を補うために与える肥料のため、効果がすぐに必要なためです。
ここまでの内容を踏まえて、たとえば追肥で化学肥料を使う際には、
- 葉を茂らせたい場合:「葉肥」である窒素(N)
- 花や実つきを改善したい場合:「花肥」「実肥」であるリン酸(P)
- 根を生長させたい場合:「根肥」であるカリウム(K)
このように、植物の成長段階に応じて必要に応じた施肥を行いましょう。
家庭菜園における元肥・追肥
与える肥料の例
寒肥
寒肥とは冬の寒い時期に、休眠期に入った植物に対して与える肥料のことを指します。寒肥は植物の成長を止めないようにするという目的で行うため、元肥の一つと考えられます。寒肥を行うと、春以降の植物の生長が良くなるという重要な効果があります。
この寒肥の仕組みとしては、冬の寒い時期は微生物の活動が鈍り、分解が遅くなっている点を利用します。時間をかけてじっくりと吸収されやすい形に栄養を変換し、春に植物が活動しはじめるタイミングで吸収されるように仕込みを行う効果があります。
芽出し肥
芽出し肥は、春先によい芽を出させるために2月下旬~3月上旬頃に与える肥料です。樹木や宿根草、球根、秋まきの草花といった植物に与えます。通常、速効性肥料を施用します。
置肥
プランター栽培等で、固形の肥料・乾燥させた肥料を植物の根元当たりに置く肥料で、追肥の一種とされています。水をあげるたびに、肥料の成分が少しずつ溶け出て効果が現れる仕組みで、そのため効果が長期間持続します。有機質、無機質両タイプがあります。
お礼肥
お礼肥とは、開花期の終わりや果実の収穫後に与える肥料です。花や果実への感謝を込めて与える肥料とされていますが、消耗して弱った植物を栄養補給を行い回復することで、株の充実や樹勢を回復させる効果が期待できます。速効性の化学肥料を使います。
肥料の使い方と注意
元肥の場合:
土に混ぜ込んで使う全面施肥と、植穴を掘って底に肥料を与える溝施肥があります。その際に、土と元肥の比率に注意し、根に元肥が達するタイミングを植物が育つ時期に合わせるように注意します。
使用する肥料は有機物になりますが、生育している植物に合った栄養素を与えることを心がけます。バランスよく混ざっている状態であればより効果があります。
追肥の場合:
追肥には、液状・粒状・固形状・スティック状など様々なタイプの種類の肥料があります。基本的には置肥として植物の根元付近に置きます。
ただし、株元に肥料を置いて与えてしまうと、肥料の過剰施肥になるだけでなく、根を傷める可能性があります。。株元から少し距離を離して置きましょう。
露地栽培の場合:水田での元肥・追肥
元肥と追肥それぞれの役割
田んぼでの水稲栽培に関しても、田植えの前に施す元肥と、田植えの後に追加で施す追肥があります。また稲に必要な主な養分に関しても、まず主要なチッソ、リン酸、カリの三種類が挙げられます。その他にもマグネシウム、カルシウムなども必要です。
稲の一生は、大別すると2つの時期に分けられます。
- 自らの体を作る栄養生長期
- 子孫(米の入った穂)を残すための生殖生長期
最初は自分の体をつくる栄養生長期のための必要な養分を与える必要があり、これが元肥となります。後半からは穂を付けて実をを大きくしていく生殖生長期に切り替わります。そこで、後半の追肥では美味しいお米の粒を増やしたり、粒を大きくするための栄養を与えます。
肥料と水が豊富にあれば稲はどんどん伸びますが、伸び過ぎは逆効果です。例えば、背丈が延びすぎて葉に太陽が当たらず、お米を作る力が落ちます。その他、草丈が伸び過ぎると、倒れやすくなります。小柄でしっかりした稲を目指して肥料をコントロールします。
また、水田では水のコントロールできるという特徴があります。肥料が効きすぎで生長しすぎた場合には、水を落として田んぼを干し、稲が肥料を吸収できなくするといったことも可能です。
水田への元肥・追肥とタイミング
基本的には、元肥は4月末〜5月頭の耕起と代かきのタイミングで行います。トラクターで土で掘り起こして柔らかくし、固さを調整するタイミングで施肥を行う場合は、「全層施肥」として長期間の効果を見込めます。
近年は、元肥と追肥を一緒に兼ねた緩効性肥料である「元肥一発施肥」が普及し、元肥のみ1回だけの施用による栽培法が主流になりつつあります。
ただし、一発肥料は万能ではないため、気温が低いなどの理由により田植え後の生育が不安定になることは起こり得ます。その場合、一般の化学肥料を分けて追肥を行うのが基本です。
一発施肥を行ってない場合や、生育不良が見られる場合、7月頃に追肥の時期が始まります。肥料が不足している場合は、稲の葉の先から色が抜け落ちるため水田に色ムラが発生します。経験と勘が必要ですが、ここでタイミングを見計らってチッソを中心とした追肥を行います。
また、雨量にも気をつける必要があります。雨量が少ない時は追肥を多く、雨量が多く土壌水分が多い場合は追肥は少なくします。
植物の成長段階に合わせた肥料を!
いかがでしたでしょうか。
植物に必要な肥料は、植物の生育状況や気温・気候等によって変化します。また、家庭菜園での栽培や露地栽培、今回例として挙げた水耕栽培などでも変わります。
ただし、基本はチッソ・リン酸・カリウムの三種類の養分が必要という点は概ねどの植物でも変わりません。植物の生長に合わせて、適切な施肥を行い元気に育成を行いましょう。
参考:
図解でよくわかる土・肥料のきほん:一般社団法人 日本土壌協会
図解 知識ゼロからの米入門:家の光協会
有機肥料とは?化学肥料との違いについて:マイナビ農業
肥料の種類や使い方、使うタイミング【家庭菜園編】:LOVE GREEN
追肥とは?野菜に与えるタイミングややり方から、その効果まで解説!:暮らしーの
元肥ってどんな肥料?その種類や使い方、使う時期など詳しくご紹介!:暮らしーの
【元肥や追肥とは?】それぞれの肥料を施す時期と方法は?:HORTI